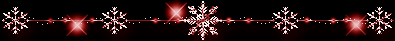| 呼びかける声を求めている。 それでも何も起きない現実に、疲れていた。 街が12月24日という特別な日を迎えて色づく中、 俺はひとりで彼女を見上げていた。 俺の願いなど叶うはずはないとわかっている。 でも、それでも―――――。 |
|
ポツン…ポツン、と雨が降っていた。 「ねぇ。」 声がする。 「外、行かない?」 俺は頷くと立ち上がる。 「雨…だね。」 少し残念そうに呟くその声。 「雪になればいいのに。」 ―――――雪。 その音に、身体の何処かが反応する。 雪…? 「手、出して?」 暗闇の中の光。 「ほら、こんなに冷たい。」 ぎゅっと掴まれる感覚。 「駄目だよ、暖かくしてなきゃ。」 呆れたように、けれど温かいその声。 「ね、………はるか。」 * その声に、目が覚めた。 部屋を見回しても、いるのは…… 動かなくなってしまった、俺の大切な人だけ。 彼女の入っている容器にそっと手を触れる …冷たい。 「なぁ。」 呼びかけた。 「外、行かないか?」 ピクリとも動かない。 「今は雨が降ってるけど。」 その白い肌がさらに白くなる前に。 「――きっと、もうすぐ雪になるから。」 お前の大好きな、雪が降るから。 色褪せない記憶。 変わらない姿。 だけど。 …抱き締めても彼女からの返事はない。 たとえ今日が特別な日でも。 奇跡など起こらない。 それでも――……。 願わずにはいられない、特別な日だから。 ―――――ゆき…。 外の雨は、雪になっていた。 |