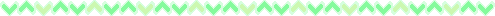
キャベツの恋+4
暇。
物凄く暇。
日課になってたヒデへのメールもなんとなくできず、私はぼーっとしてた。
だって、やっぱり彼女持ちの男が他の女とメールするのはまずいでしょ。
いくら、その女に恋愛感情を抱いてないとはいえ。
「あーっ!やだやだっ!」
私はひとり、ベッドの上でバタバタした。
何でこんなにめそめそしてんだ?いいじゃん、親友に彼女が出来たってこと。
もっと喜ぶべきなんじゃない?何でこんなにしょげてるんだよっ。
ヒデに対して、おめでとう、と言ってあげるべきだったのに。・・・なんでできなかったんだろう・・・。
麗菓の顔がぐるぐる笑う。ソフトウェーブかかったセミロングがふわっと揺れてる。
麗菓の顔がぐるぐる笑う。ヒデが嬉しそうに笑う。
皆が祝福してる。璃舞が。絽亜が。羅弥が。
皆が笑う。
「ッ!!」
私はベッドから飛び起きた。財布を掴んで、階段下りて、玄関で靴を履く。
「瑠那?」
「ごめん、ちょっとジュース買ってくる。」
台所から出てきて心配そうに聞くお母さんに、私は素っ気無くそう答えた。
「そう。早く帰ってきなさいよ?もうすぐご飯だから・・・」
「うん。大丈夫。」
家の中に居たら、私はこのまま壊れてしまいそうだから。
「じゃあ、行ってきます。」
だから、少しだけ外に行かせて。
「ふぅ。」
家飛び出して、近くの公園の自動販売機で烏龍茶を買った。
公園のベンチに座って飲んだ。
冷たくて、ほろ苦くて、おいしかった。なんだか気分も少しすっきりしたかも。
ポケットのケータイを見る。何の着信も無い。
…、私からメールを送れなかった日は、ヒデからいつも送ってきてくれたのに。
今日は来てない。
やっぱり彼女が出来たから?麗菓がいるから?私はもう必要ないの?
何で?私はヒデにとっての――親友じゃなかったの――?
「あ、そーか。」
わかった。
何でこんなに辛いか。
私は、親友のヒデが麗菓にとられちゃった気がしてたんだ。
だから、こんなに淋しくて、切なくて、悲しいんだ。
わかった。
私ははぁ、と溜息をつくと立ち上がった。いつまでもここにこうしてるわけにはいかないもんね。
お母さんに心配かけちゃうし。
――あのときみたいに。
でも、まっすぐ帰る気がしないで、少しだけ遠回りした。
人が多い道を歩いた。
私、人ごみって凄い好き。雑踏の中、ぼーっとしてるのが大好き。
ざわざわざわざわ、世界が揺れてる中、私だけがずーっと止まってるの。ずーっと。
そんな私がいつも通り人ごみの中、ゆっくり歩いてた時だった。
「…あれ?」
見覚えのある姿。
「璃舞、じゃんね…?」
でも自信が無かった。何でかって言うと、いつもの璃舞からは考えられない姿をしてたから。
胸のがーって開いた服着て、上からジャケット羽織ってて、それで下はもう少しで見えそうなぐらい短いスカートに、ほっそいブーツ。
全身シックに黒で決めてるんだもん。私らの中で一番そういうカッコをしそうなのは羅弥だけど、一番しなさそうなのは璃舞。
…?どしたんだろ?
「璃舞ぁ!」
私は璃舞に声をかけた。でも、人々の雑踏で消されてしまった。
「あー・・・もうっ。」
イライラする〜。人ごみってこういうときは不便だよね…。
「璃舞!!」
私はもう一度声をかけた。でも、璃舞は気付かない。あーもう!気づけぇええええっ!!
「璃舞―っ!!」
璃舞は、気付かなかった。
そして、側にいた男に話し掛けた。
男は顔見知りの様子で、璃舞と楽しげに話している。
しかし、その男もなんてか、ねー。髪の毛は金色に赤が入ってるし、服はランニングにだふーっとしたズボンだし。赤紫っぽい色の。もう秋…ってか弱冬なのに、寒くないのかなー…。
そんな私の考えをよそに、璃舞はその男と一緒に店と店の間にある階段へと入ってった。
「璃舞?」
私は慌てて駆け出した。
その階段は、地下へと続いてた。私はふと上を見た。そこには、『Ruby』って書いてある。
「ルビー?」
なんか聞いたことあるなぁ。誰が言ってたんだっけ?
あ、そーか。羅弥だ。羅弥が言ってたんだ。入学したすぐの頃。一緒に行かないかって…
『メジャーデビューしてない奴らでも、いい曲作るやついっぱいいるんだ。だから、行かね?ライブハウス、「Ruby」!!』
!!!!!!!
そうだ!ライブハウス!!!
ってそーか、だから璃舞もあんなカッコしてたのか。
でもあの羅弥が誘った時、一番嫌そうな顔したの璃舞だったのに。意外だわ、ホント。
私はそーっと階段を覗き込んだ。
中はちょっと暗くて、どうなってるか見えなかった。
「コワっ。」
私はちょちょ、っと駆け足で遠ざかってみてから、また家に向かって人ごみの中歩き出した。
だって、別にライブ見たいとか思わないし。
怖い思いして単身乗り込んで行く気なんか何にも起きないもん。とっとと帰ろ。
でも、なんだか璃舞の意外な一面発見!っていう感じだった。
そうだ。人って、見た目だけじゃ何も判断できないんだ――。
ヒデの気持ちとか、私が……考えるようなモノじゃなかったんだ。
私のことを一番の親友と思ってくれてる、っていう…馬鹿みたいな、自惚れ。
なんて、今の状況をなんとかヒデと結び付けようと頑張っていた。
独りじゃ淋しすぎて。
***
「あ、あれっ……」
ぼーっと歩きながら、色々考え事してたら、気付けばヒデの家の前だった。
「私、馬鹿……。」
そうだ、いつも何かに辛くなったらヒデの家に来てたんだ。そして夜まで飲み明かしたり…とか。未成年だけど。
今じゃもう…彼女のいるヒデに…そんなこと、できるわけない。
でも、でも……。
独りじゃ、もう、無理だよ―――――。
私は独り、膝を抱えて蹲った。ヒデの家の前で。
「あれ、瑠那ちゃん?」
声がかかったのは、それから間もなくだった。
私が顔を上げると、そこにはヒデとそっくりな顔をした人――そう、ヒデの2コ上お兄さん、千寛さんが立っていた。
「どうしたの?」
優しい、声。いつもこの人はそう。私が何か泣いてると、ヒデよりも…ずっと、助けてくれた。
どこからの帰り道だろうに。家に入りたいだろうに。私のことを無視しなかった。
「千寛さん…」
ずっと、涙は我慢してた。
流したら、もう駄目だと思ったから。
それか、何か他のもののせいにしてた。
認めたら、もう駄目だと思ったから。
でも、もう限界だった。
「瑠那ちゃん?……泣いてるの…?」
千寛さんの戸惑った表情。私は千寛さんの胸に飛び込んでいた。
千寛さんは拒絶する風もなく、理由を聞くでもなく、そっと私の髪を撫でてくれた。
少し寒くなった初冬。なんだかやけに温かかった。
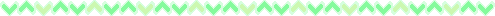
コメント:
2004.05.03.UP◇■
シリーズ化(?)することにしたキャベ恋。
ついに飯田千寛君登場ーッ!
なんか名前聞いたことあるって思ったアナタは凄い。