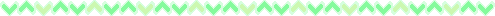
キャベツの恋+5
「そっか…」
場所を変えて…近くの公園に行って、そこで、私の気持ちを全部千寛さんにぶちまけた。
「……瑠那ちゃんは、偉人のことをどう思ってるの?」
千寛さんの優しい口調。私はじっと千寛さんを見つめた。
「どう、って……?」
「瑠那ちゃんは、千寛のことを…どう好きなのかな、って思って。」
私は少しムッとした。千寛さんならわかってくれると思ったのに。
「それは、親友としての好き、です。」
「――なら。」
千寛さんは私をじっと見つめ返した。声のトーンこそ優しいものの、瞳は真剣そのものだった。
「淋しくて、苦しくても…絶対に、瑠那ちゃんの居場所はなくならないよ。」
「え?」
「瑠那ちゃんが本当に偉人のことを、ただの親友だと思っているのなら、彼女が出来ようと親友っていうスペースがどうこうなるものじゃないから。今はつらくても、絶対に大丈夫。」
「………。」
それって、どういう…?
「―――――でも…」
千寛さんは、私から目を逸らした。空を見上げる。…星が、既にいくつも出てた。
「もし…瑠那ちゃんが偉人に…恋愛感情を持っているとしたら……」
先は聞かずともわかった。
「夜、眠れない。…偉人の彼女の…麗菓さん、に、対して異常な嫉妬感情を持つ。わけもなく哀しくなる。偉人の顔が何をしててもちらつく。」
頭では何も考えないことにした。空を見上げてた。
「そういう恋愛感情を持っているとしたら――、それは、僕にはもう何も言えない。」
結局は、それなんだよね。私が全部考えるんだ。
「麗菓さんから何をしても偉人を奪い取る、とか…諦めて親友の位置につく、とか…方法は色々あるけど、ひとつだけわかっていることは……そういう『好きだ』っていう気持ちは、何をしてても消えないっていうこと。忘れようと思えば思うほど、全てを思い出してしまうということ。」
そこまで千寛さんが言うと、ヒデの家の側の公園に、静寂が訪れた。
こんな時間の公園なんて、私たちぐらいしかいないもんね…。
そうやって、ぼーっと空を眺めてた。気持ちがなんだかすーっとしてくる。私、どうしたかったんだろう。今なら考えられる?
どうして――こんなに辛いんだろう。
本当に、時さえ待てばこの気持ちは落ち着くの?ヒデが誰かと結婚しても?
大丈夫なはずだよね……だって、私はヒデの一番の親友。
そうだ。私はヒデの一番の親友なんだ。だからつらかったんだ。ヒデの"一番"が私じゃなくなったような気がして。
親友の座は揺るがないってわかってたのに、だから不安だったんだ。
大丈夫。ヒデなら、彼女と私を…ちゃんと、両立させてくれるもんね――。
「ヒデの家、行きたいです。」
私は千寛さんに向かって笑ってそう言った。
「わかった。」
千寛さんもにこっと笑った。私の中で何か吹っ切れたの、気がついたのかな…?
そして、私たち2人が立ち上がったとき、それは聞こえてきた。
「やぁだぁ…」
「!?」
私たちは声も出さずにそっちの方向を向く。それは、ちょっと離れたベンチの声だった。
今来たようなカップルが、一組。と言っても街灯に照らし出された影ぐらいしか見えないんだけど。
そのとき、女が甘い声を出すのに被せて、男が――キスをした!!
「!?!?!?!?!?!?」
私と千寛さん、声も出さずに驚きふためく。
男は唇を離すと、
「そんな甘い声で…俺を誘ってんだろ?らや……」
「えっ!?」
自分であんまり自覚はなかったけど、私は思いっきりでかい声を出して叫んでいた。
だって、今、男、何て言った?
「(ちょ、瑠那ちゃん。まずいよ。)」
「(えっ、だって、千寛さんっ…)」
だって、だって、今、男、
「誰だぁ?そこにいんの。」
男のドスの効いた声。
私と千寛さんは無言で頷きあった。―――――逃げよう。
私と、千寛さんは振り向きもせず全力で走った。その背中に、女の甘い声がかかる。
「気にしなくていいじゃなぁい。見られてた方が燃えるしぃ…」
この声は……やっぱり!!
男は、女を『らや』って呼んだ。『らや』なんて名前、そうそうあるもんじゃない。
私が知ってる『らや』なんて1人だけ――羅弥!!
声も、あの羅弥だった。
どういうことなの?何で、こんな時間にあんなところで――?
ってそんなの、答えは一つか。あれは羅弥の彼氏なんだ。
でも、男の前では羅弥があそこまで性格変わるなんて……意外、じゃ言い表せないよ、もう。
***
「ちょっとだけだぞ?」
「わかってるってば!犬見たら帰るからぁ!」
そして――ヒデの家に着いた私にさらに待っていたものは、過酷すぎる現実だった。
「ただいまーっ。」
「あら、偉人。遅かったわね。」
「今日、ちょっと人連れてきたから――」
「あらあら!偉人、彼女!?」
ペコリっと頭を下げる、麗菓。
「その、偉人君とは……仲良くさせてもらってます、葉月麗菓です。」
「れ、麗菓さんッ!!」
ヒデが慌てふためいて、顔を真っ赤にさせてる。
「どうぞどうぞ、何もない家ですけど。」
ヒデのお母さんがにこにこしながら、ドアを閉めた。
「…千寛さん。」
「瑠那ちゃん。」
「私、帰ります――。」
「えっ?」
「……ヒデには、私が今日ここにいたこと、内緒にしといてくださいね。」
「瑠那ちゃん!?」
「ありがとうございましたっ。」
全速力でそこから走った。
何も考えたくなかった。
麗菓と一緒にいるヒデを、見たくはなかった。
何が男女の友情なんだろう。
私が今、ヒデに抱いている感情は―――――。
***
「ただいまっ…て。」
「瑠那っ…遅かったわね…」
お母さんが玄関に立っていて、私がドアを開けた瞬間抱きついてきた。
「よかった…帰ってきてくれて…」
あぁ、お母さん…ごめんね……。
「ありがとう。」
私はお母さんにお礼を言った。心からのお礼を。
「心配かけて、ごめん――。」
昔、…って言っても中学の時。
私がいじめられてたとき。
学校に行きたくなくて、そう、さっき烏龍茶を飲んだあの公園で、私は1人、学校をサボッてた。
そしたら、学校から家に電話が行ったらしくて、お母さんは――ずっと、ドアの外に立ってた。
学校が終わる時間に家に帰った私を、…夏だったから…汗びっしょりのお母さんは、怒ることなく、抱き締めてくれた。
「よかった…帰ってきてくれて…」それだけ言って。
私は、お母さんに…どうして相談しなかったんだろう…。そう思って、本当に後悔した。
お母さんには、お姉さんがいた。
お母さんのお姉さんは…学校で、いじめにあっていた。ただ、人より背が高かった…それだけで。
お母さんが、たった10歳だったとき、お母さんのお姉さんは…中学校で、またいじめられて、
それで―――――自殺してしまった。
お姉さんは、「ちょっと外の空気吸ってくる」と言って、5時間以上も帰ってこなかった。
お母さんや家族はいなくなってしまったお姉さんを探すために町中を走り回った。けれど見つからなかった。
そして、お母さんが誰よりも最初に家に戻ってきた。何か嫌な予感がしたからだ。
でも、そのときには、玄関の前で首を吊っているお姉さんの姿が…あったという。
もし、誰か1人でも家に残っていれば――…そんなことにはならなかったかもしれないのに。
お母さんのお姉さんは、淋しくて、1人町を歩いて、そして帰って来たら、誰もいなかった。
そんな状況で、死んでしまったんだ…。
その話は、数日後にお父さんから聞いた。
「弥生(お母さんの名前)は…だからか、帰ってくるはずの時間に帰ってこないと、必要以上の心配をするんだ。」
私は、そのとき、ちゃんと時間には戻ってこようって…何があっても戻ってこようって思ったのに…。
「あの子たちのこと?」
「え?」
「ほら、……女の子、4人と…」
食事をしながら、お母さんが心配そうに訊いてきた。
「大丈夫、もう仲直りしたの!向こうからごめんって言ってきてくれたんだよ!!」
「えっ!……よかったわね……」
お母さんは本当に嬉しそうににっこりと笑ってくれた。私も笑い返した。
「じゃあ、今日はどうしたの――?お母さんに、もし、言えることなら…言ってみて…」
お父さんは、まだ仕事から帰ってきてなかった。
お母さんになら、話せる。……お父さんにこういう恋愛関係のこと話すのには勇気がいるけど。
「あのね…」
私は、また、話した。
「そう…。瑠那は、偉人君が好きなのね。」
「えっ?」
「親友として、とか、恋人として、とか、じゃなくて…。ただ、偉人君のことが好きなんでしょう?」
私はお母さんを見つめた。
「好きだと思うと、独り占めしたくなる――当然よ。」
「それが、親友への気持ちでも?」
「当然よ。親友でも、友達でも、家族でも、……もちろん、恋人でも。」
「この気持ちがどっちなのかって考えなくてもいいの?」
お母さんは柔らかに笑った。
「…考えてわかるものじゃないわ。瑠那が偉人君にどこまで求めているか。それだけじゃないかしら。……自分で、ふとした瞬間に気付いてしまうものよ。」
「ふとした瞬間?それって、やっぱり麗菓に対する嫉妬心とか……?」
「いいえ。嫉妬心は、ただの友達にでも起こるものよ。……プラスの心で確かめてみればいいと思うわ。」
「プラスの、心…?」
「そう。……もし、瑠那が偉人君に抱き締められたいとか…そう思うのなら……それは、親友への思いじゃないわよね。」
ヒデに――抱き締められたい―――――?
「私が助言して、それで気づくことじゃないけれど……でも、恋愛ってそういうものじゃないかしら…。ずっと、その人と暮らして行きたい。その人の子どもを産みたい…とか、ね。」
あぁ、そうか。
そういうことか。
「ありがとう、お母さん。」
ちょうど私は御飯も食べ終わった。箸を綺麗に並べて置く。
「ううん、瑠那がつらくなったら、いつでも相談してね。」
「うん。」
私は笑って頷いた。お皿とか、お茶碗とかを流し台に持っていて水を掛けておく。
お母さんに相談してよかった。千寛さんに相談してよかった。
今は、ヒデを親友だと思っていよう。…もし、この先……ヒデにそれ以上を望む私の気持ちがあれば……
そのときは、気持ちを抑え込まずに、向かい合おう。
自分とも、麗菓とも。
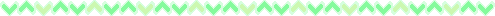
コメント:
2004.06.25.UP◇■
久しぶりのアップ、キャベ恋。
がんばれー瑠那ー。ってな感じかい?